SPECIAL ISSUE
特集
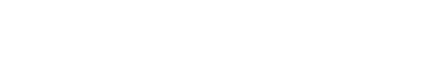
演劇のリアリティとアクチュアリティ
~三浦基が今語るイェリネク『光のない。』~

フェスティバル/トーキョー12で初演され、今秋再演が決定している地点『光のない。』。
ノーベル賞作家エルフリーデ・イェリネクが東日本大震災と原発事故を受けて書いた長大なテキストを舞台化したこの作品は、初演の際、わずか3日間の上演にも関わらず観客からの圧倒的支持を得た伝説的作品です。初演から2年が経った今、この作品を再演するのはなぜか。三浦基自身が改めて『光のない。』について、演劇が背負うべきアクチュアリティとリアリティの在り処について、早稲田大学文学学術院教授の佐々木敦氏と語りました。
日時:2014年10月2日(木)14:45-16:15
会場:早稲田大学 小野記念講堂
主催:早稲田大学演劇博物館、早稲田大学演劇映像学連携研究拠点
舞台写真:松本久木
岡室:本日はお忙しい中、早稲田大学演劇博物館と、早稲田大学演劇映像学連携研究拠点の主催によります演劇講座にご来場くださいましてありがとうございます。
今日は三浦基さんという素晴らしいゲストをお迎えしまして、本学教授の佐々木敦先生に聞き手を務めていただきます。タイトルにもありますように、イェリネクの『光のない。』という作品のお話が中心になるかと思います。三浦さんの地点によりますイェリネクの『光のない。』は2年程前にフェスティバル/トーキョーで初演され、わたしも拝見しましたけれども、すごい作品でした。本当にすごいとしかいいようのない、みたことのない劇作品であったと思います。近々KAAT神奈川芸術劇場で再演されますので、まだご覧になっていない方、あるいは既にご覧になった方も、そちらのほうにお越しいただければと思います。それでは早速、今日の演劇講座を始めたいと思います。
どうぞ最後までお付き合いくださいませ。
佐々木:どうも、ご紹介を受けました佐々木です。よろしくお願いします。
三浦:三浦です、よろしくお願いします。
佐々木:結構急に決まった講演会なんですが、満席になって非常によかったなと思っています。本日は90分、『光のない。』という作品について、三浦さんにお話をうかがっていきたいと思います。
三浦さんが演出・代表を務めていらっしゃる劇団「地点」は、京都を拠点にしている劇団ですけれども、近年、京都・横浜・東京など、また海外でも非常に旺盛な公演を行っている劇団です。その中でもこのエルフリーデ・イェリネク作の『光のない。』は、僕は2年前に拝見しましたが、三浦さん曰く「場外ホームラン」だと。自ら思えるほどの納得のいく作品だったんですね?
三浦:そうですね、あまりこういう場では言わないようにしておきますけれども。これは本当に色々な巡り会わせがあった作品で、それまで自分が考えてきたこと、意識化できなかったことも含めて爆発したことは間違いないです。
佐々木:原作を持ってきました。エルフリーデ・イェリネクの『光のない。』という戯曲というかテキストで白水社から出版されている翻訳本です。今日は映像も持ってきていただいているということで、準備ができているようでしたら、まず映像を見ましょう。
佐々木:これは映像だけだと分かりにくいかもしれないですが、すごい巨大なセットなんですよね。
三浦:そうなんです。ちょっと解説しましょうか。(舞台写真を見ながら)

とにかくイェリネクというウィーンのノーベル賞作家がいまして、ドイツ語圏の演劇の代表格なんですね。ドイツ演劇といえば、ハイナー・ミュラー、その前にブレヒトがいる。ブレヒトがいて、ハイナー・ミュラーがいて、その後にイェリネクという系譜があるんですが、それはポストドラマ演劇と呼ばれるような演劇で、つまり私たちが想像する演劇の形式とはちょっと違うんですよね。物語があって、それが回収されていくようなものではない。一言で言えば難解なわけです。『光のない。』という作品も翻訳されて日本語になり、翻訳賞ももらっていますが、それも一読すると、まあわからない作品なんですね。
そういったことをまず一旦おいておくとして。僕は演出家で、2年前にこの作品の依頼がフェスティバル/トーキョーからあったとき、まだ翻訳されていなくて、だいたいの内容だけ聞いただけなのですけれど、やりますと言ったわけです。原発や震災をモチーフにした作品というので、当時のプロデューサーに一応確認したんです。それって福島とか、具体的な何か村の話?と。そしたら、いいえ、もう福島の「ふ」の字も出ていません、モチーフにしているだけです、と。反原発を訴える社会的なものではまさかないよねとも聞いたんです。そうしたら、ええもちろんそういうものではないですと。ともかくイェリネクは以前から信頼している作家だから、僕がやらないで誰がやると思って決めたわけです。
あえて堂々とプロセニアムの劇場で上演するという覚悟
三浦:次の問題は、規模の大きい企画だったので、劇場をどうするかということ。具体的なテクニカル面から話を進めていったわけです。最終的には、池袋の東京芸術劇場でやろうということになって、それが大きな問題だったわけです。
みなさん、僕は決して難解な作品ばかりやっているわけではなくて、『はだかの王様』というこども劇もつくっているんです。ワークショップで100人くらいのこどもたちと舞台美術をつくるっていう企画でした。ワークショップのときに、劇場の絵を描いてよといったら、みんないわゆるプロセニアムの劇場を書くわけです。だれも能楽堂や歌舞伎小屋は描かない。つまり演劇というものは額縁なんだと。緞帳があって、客席があってというような。僕がやってきたことはどっちかっていうと、ブラックボックスのような、フラットな状態の箱を使って、どれだけ舞台と客席の境界線をなくすかとか、そういったことで演劇をつくってきている自負があったんです。でも、イェリネクをやること、ポストドラマ演劇をやるってことはどういうことなんだと、潜在的にも意識的にも考えて、よし、プロセでやってみようと。
佐々木:むしろ従来の演劇が行われてきた場所でやってみようということですね。
三浦:イェリネクが考えている演劇の解体であったり、劇場文化とか、どうして演劇がこのようなことになっているのか、という問題をおそらく彼女の文脈の中で堂々と考えなければいけない。それを真っ先に、空間のことで言えば思ったわけですね。東京芸術劇場のプレイハウス、これは典型的な劇場ですね。舞台があって、緞帳があって。それで、客席をつぶして張り出し舞台を設えました。ラッキーなことに、東京芸術劇場は防火シャッターがあったので、これを緞帳の替わりに使おうと思ったわけです。これが上がると、セットが後ろに組まれている。壁が四方を囲み、床が上がっていて、という空間を作ったわけです。(写真下部を指して)そしてここに足が見えていますよね、これ合唱隊が寝転がっているわけです。

佐々木:三輪眞弘さんが音楽監督を務めていて、その一環ですよね。こうしてみると異様な感じですね。
三浦:皆さんぽかんとしていますね。何を説明しているんだろうという感じだと思いますが。僕にしてみれば、いままで説明した中に、演劇の歴史が詰まっているわけです。つまり、プロセの芝居で前を張り出して、緞帳をシャッターに変える。ワーグナー以降、オペラのオーケストラピットというのは、半地下にうめたんですね。そこに、合唱隊を埋め込んでしまうと。舞台は四方壁で覆われていて、いわゆる劇場の照明が見えないようになっている。こういったことを必死に美術家とスタッフと考えたんです。そのときの打ち合わせには、『光のない。』の文学性は全く関係ないわけです。どうしたら、プロセニアムの劇場で芝居を作ることができるのか。
例えばモスクワ芸術座は、平土間と呼ばれる1階席が400席、そしてバルコンと呼ばれる垂直に立つ2階席3階席を併せて約1000席なんです。日本はハコばかり作っているというのは長年言われていることですが、平土間で600~800席作ってしまうわけです。2階席も奥の方まで作って合計で約2000席。どこの劇場もでかすぎる、結局後々にリニューアルして小さくするという、本末転倒なことが起こっています。そこで出てくるのがマイクですよ。ピンマイク、それで堂々とストレートプレイをやっている。これは自分たちで自分たちの首をしめているんじゃないかという、怒りというか、反発というか、だからプロセで成立する芝居を作るにはどうすればよいか、ということを考えたんです。
例えば中央に立っている俳優は、床に台詞を当てています。このように、四方を壁で囲うことによって、声を床にあてて跳ね返して、それが天井から跳ね返ってきて生声が聞こえるという仕組みをつくる。後ろを向いたときは天井の壁に当てるとか。奥のほうに行くとさすがに遠いので、そこには盗みのマイクを仕込んで、ばれないように声をひろってそれをスピーカーから出す。そういうことに現場の演出は必死になるわけです。

いまこの写真で奥の四角いスクリーンが上がってきているのがわかると思いますが、あそこは最初真っ黒な闇で、スクリーンがあがっていくと光がさしてきます。灯体の光源は見えていませんが、実はあの奥に沢山の照明が仕込んであるんです。様々な方向から狙って、このような効果を作っているんです。そういうことをやるということが、なぜ演劇をプロセで見るのかということに対する応答だということです。
イギリスでもフランスでも、ヨーロッパの演劇は中世からの建物を引き継ぎ、中身を改装して、プロセ若しくはプロセでない劇場を作り、さまざまな現代演劇を成立させているわけです。日本で演劇をやるというと、小劇場って聞いたことあると思いますが、なんとなく狭いスタジオでやる、演劇と呼ばれるものは商業演劇で、こういったプロセの劇場でやるっていうように分かれていると思うんです。そこに一撃を与えないといけない、という思いが当時の演出の通低音としてあったんです。
電気VS俳優 強制的な同期で媒体としての俳優を見せる
三浦:
音楽監督の三輪さんとも相談しました。一番最初に出てきたアイディアは、低周波マッサージ器を改造した装置です。これを腕に俳優が付けて、電気を通すとびりっとなって、腕が動くんです。そこに鈴を持っているとシャランと鳴ると。それがようやく原発の問題とか、電気の話につながっていく。そして合唱隊。私たちが「合唱隊=コーラス=コロス」と呼ぶものですね。人が何かをしゃべるときに、「わたしはつらい」という台詞があったとする。「わたしたちはつらい。なぜならば戦争があったから。なんて悲しいんだろう」、これを喋るとなると2000年前まで遡れば、ギリシア悲劇ではコロスがその役割を担っていたんですね。100人の合唱隊が「風が吹いてつらい」と言いだすとかね。それは一個人の主張で演劇の台詞があるんじゃなくて、合唱とか、群唱と呼ばれるような形で、群れの人たちが観客に何かを届けるというタイプの台詞なんです。そういうこともおそらく『光のない。』の中には書かれていて、イェリネクはなかなか「わたしはつらい」とは言わないわけです。で、「どうも私たちはつらい」というような台詞があって、それを台詞にしたり、合唱隊の人たちの言葉ではない歌声と絡ませたりと、発語の根拠というものをすごく考えました。最初に説明したPiriPiriと呼んでいるこの装置は、電気を流してシャンシャンシャンとやっているんです。人が同時にしゃべるのは群唱といってもなかなか難しい。「わたしはつらい」というのを同時に言うのはとても難しいんです。同時というのは数学的に、0.1秒の狂いなくということです。
佐々木:完全にぴったりということですね。
三浦:そうですね、同期しているということ。この装置は、本当に同時に鳴るんですよ。こういう風に倒れている人が、電気がくるとぼんぼん動くんです。

佐々木:本人の意思と関係なしに動くんですね。しかもそれが電流という電力というものによってなされているところに、この作品の背景とつながってくる部分があるということですね。
三浦:外圧といいますか、そういったもので演技を組み立てていくということをしたのはこの作品が初めてだったし、作品の主題ともすごくマッチしました。
プロセでやるためのセットをどういうふうに考えるのかとか、日本の少し大きすぎる箱の中で声届かねえよってあきらめて、小劇場出身だし、やはりああいうのはやらないってひねくれるんじゃなくて、いま世界を席巻している作家、しかも日本を主題にかかれた作品をなんとかヨーロッパの文脈でも成立させられないか、という闘いがあったということです。そして、コロスの問題ですね。主体性のある「わたし」が台詞をしゃべるのではなく、「わたしたち」がこう思っているらしいということを表現できないか、と思ったんです。合唱隊と、音楽監督が編み出した演奏装置、俳優の身体にまさに電気を通すという外側の圧力によって、俳優を媒体にして伝えられないかということを説明したかったんです。
佐々木:地点が「アンダースロー」を作ったのは去年でしたでしょうか。地点は京都に「アンダースロー」という名前のアトリエ兼ミニシアターを作って、そこで小さな公演を頻繁に打っているんですね。そういったもともとライブハウスだったようないろいろな使い方のできる小さな空間、小劇場的な空間でプロセニアムとは違った様々な実験をいろいろな人たちとやっているわけですよね。今の話は、三浦さんはむしろそういったところから出てきている人なんですけれども、あえて巨大なプロセニアムの劇場で、いままで自分がやってきたことの発展系としての実験をやってみたということですよね。
三浦:そうですね。演劇をやっていると、そういうことを真っ先に気にしてしまうんです。本当は今日はイェリネクの文学的な部分から話すべきなんでしょうけれど、どうしてこういうことなのかと、漫然と大きい企画で大きい声でやっているわけではないということをまずはお話したかったんです。
テキストを〈上演〉するために
ーー地点の作劇方法について(1)
佐々木:いまですね、すごく具体的な舞台装置の話と照明の話をしてくださったんですけど、三浦さんはそういう話から入ってしまったとおっしゃいましたが、でも実際そういった問題は全てこのイェリネクの『光のない。』というテキストの文学性、言葉の持つイメージ、その背景にある様々なテーマ群というものと実はものすごく有機的に結びついていると思うんですね。ですから今の説明の中でも、実は『光のない。』の初演を見ている僕からすると、実はもう作品の中身の説明にかなり入っているなと思いました。
いま、先んじて、外側といいますか、演出の話になりましたが、地点がこの『光のない。』初演のときには俳優は5名、いまは一人増えて6人になって、今回6人でやるんですけれども、ここは地点の非常に特異なところと言っていいと思うんですが、シェイクスピアをやる時も、チェーホフをやる時も、どの戯曲でも5人でやる、そしてこれからは6人でやるということなんですが、『光のない。』のテキストは、AとBという二人の人物が、交互にほとんどモノローグといってもいいような言葉を発し続けるというテキストなんですけれども、それを5人で演じて、今回は6人で演じるという、もとの戯曲に対して、俳優の発話にそれをどういう風にトランスフォームしていくのかというところへ話を進めたいのですが。
三浦:チェーホフだとだいたい10人以上の登場人物がいて、シェイクスピアだと20人くらい。これをまあ5〜6人にする作業、これはなんとなく想像がつくでしょう。現代から見ると長ったらしいから、ちょっと抽出して短くレジュメしましょうというのは想像できると思うんですね。でもイェリネクの場合ちょっと特殊で、AとBの登場人物が書かれてあるのですが、それが本当にダイアローグになっているのか。設定、ト書きと呼ばれるようなものがほとんどないんです。
佐々木:そうですね、AとBだけが続いているという。
三浦:なので、これを何人でやるのかという問題は、ちょっと特殊だったと思います。ただ、前提を話しておくと、古典であろうと、イェリネクのような現代的なテキストであろうと、基本的には僕はいま信頼できる継続した作業ができる俳優6人、当時は5人ですが、いるわけです。で、5人とか6人でできることならやればいいという考え方なんです。もうちょっとおこがましくいうと、このメンバーでなんでもやるという感じです。イメージで言うと、地点というルールがあって、6人のルールに全てを納める。うーんどういったらいいんでしょうね……まあ、こちらのルールでまわしていくというのが基本的にはあるんです。
それからイェリネクの場合は、彼女自身が「私の書いたものは演劇のテキストであるけれども、上演のためのテキストではない」と公言しているんです。この言葉はとても重い言葉なんです。これを言える生きている劇作家というのはよっぽどのことですよ。普通は劇作家が生きていると、書いたことと違うとか、自分のイメージと違うと言う訳だけど。そういうことではないところまで、演劇の世界が行ってしまっている。ポストドラマ演劇を一言で現せと言われたらこういうことなんだと思う。そういうテキストに対して、こっちは全力でやっていくしかないというのが正直なところです。
佐々木:こちらは上演しなくてはならないほうですからね。
三浦:もう少し説明しますと、つまりイェリネクも、古典とかそれまでのタイプの演劇というものが、書かれてある記録の通りに再現されたところで、今日、息をしている観客にとってリアリティがあるのかどうかということは必ずしも保証されないでしょう、という経験をしているわけです、客席で。自分が演劇をイメージして書いた文章というのがあるのだけれども、それをどのように観客に伝えるかはやる側の人間、パフォーマーの側の問題だということを明言したんだと思います。ですから、イェリネクには、初演時も今回も会っていませんし、何のやり取りもない。もちろん著作料は払っていますけど、関係ないわけですね。そういう立場に立っている作家というのは稀有だし、尊敬できるなと思います。次に、それをどのように発語するか問題なんですが、これは見ていただかないとなんとも。
佐々木:とにかく特異な台詞というか言葉ですからね。
三浦:先ほどの短い映像を、舞台装置の説明もしましたのでもう一度そういう視点から見てみたらよいかもしれませんね。
(動画一時停止)
三浦:
「め~」というのは合唱隊の歌声なんです。
佐々木:足を出していた人たちの声ですね。台詞の他の音は、PiriPiriと合唱隊の人たちの声しかないんですね。
三浦:基本的には。あとはガイガーカウンターの「ジジジジ」という音ですね。ガイガーカウンターは音響で流しています。
(動画一時停止)
三浦:「海が海がみみみ耳水水?自らの」というのは『ゴドーを待ちながら』のラッキーのパクりです。知らなかったら『ゴドーを待ちながら』を勉強して。素晴らしい作品だから。しゃれですよねいってみれば。そういうエクリチュール、文体になっている。意味が二重、三重になっているから。どもりは書かれていないんですけれど、注釈の嵐なんですよ。これは何とかの引用であるとか、調べだしたらきりがない。
(動画一時停止)
三浦:これはね、普通に言ってくれって言っています。
佐々木:普通にって(笑)
三浦:身振り、指を指すジェスチャーに、ここは重きを置いているわけです。
(動画一時停止)
三浦:今のが先ほど説明した、PiriPiriです。ここの台詞も普通にしゃべっていますけど、マイクという電気を通してしゃべります、この後このままずうっとしゃべると飽きるので、(三浦マイクから口を離して)「電気が通っていないので、大きい声でしゃべります」という演出を入れます。(マイクを口に戻して)というような操作によって「聞いている?」ということになるんです。ここに感情が伴う。なんであいつら普通にしゃべらないんだと受け取られるんですけれども、動機としてはこうした手順を踏んでいるわけです。
(動画一時停止)
三浦:今のシーンではヘリコプターの音響が流れています。電気を通して効果音として流れるので、とにかく俳優は叫ぶしかないね、ということです。もちろんヘリコプターの効果音を流せとは書いていないんです。でも、ここは文章的にも内容的にも、原作でもクライマックスに近いわけです。その場合、演出としては叫びたいわけです。何が何でも、とにかく叫びたいシーンなわけです。そのために、ヘリコプターを出す。そうすると喧嘩できるから。蛇口をひねれば水は出るんですけれども、蛇口をひねったら、上からシャワーが出るとか、回路を沢山つくる。そのことによっていろいろな感情が同時に爆発するようなことを資質としては好んでいるんだと思います。
文章を読んでいる本読みの時点では、ここは感情のピークであると感覚を持っているんです。それは一般読者といっしょですね。それをどういった手管を使って提出するかっていうときに、演出のやる作業というのは、なにがなんでもヘリコプターということ。一番最初に音響スタッフのチーフに、今回はヘリでいきますのでよろしくと伝えるわけです。で、音響のチーフはヘリの音を10種類持ってくるわけです。どれがいいですかと。ということが作業としてあって、それを組合せたときに、みんなが想像していなかったものが出来上がったときに作品というのはぐんっとあがっていくわけです。
『光のない。』という作品は震災から間もなく、すぐに上演したし、観客のなかにもコンテキストが出来上がっていたし、迷いもあったし、怖さもあったし、後ろめたさもあったんですね。そういった緊張感の中で奇跡的にぐんっと形になってでたというのが、正直なところ。手前味噌ですが、これは場外ホームランであると。僕が打ったというよりも、誰が打ったかわからないけれども、球が遠くまでいっちゃった。もちろん観客の力でもあるわけですが。そういうことだと思います。
集団創作と停滞
ーー地点の作劇方法について(2)
佐々木:例えば、チェーホフだったら、登場人物がいて、物語もあるし、登場人物のキャラクターのテンションもあるわけで、それをどうするかっていう話になると思うんですが、イェリネクの場合、『光のない。』に限ったことではないですけれども、彼女が書く戯曲は、大方は難解な、誰がしゃべっているかもわからないようなものが多いじゃないですか。その言葉を実際に俳優が発話して舞台に上げていくというときに、テキストにもともと内在しているある種の論理というか、この場から考えうるもの、導き出すことができるものというのをどれだけ思いつくことができるのかということがひとつ。それを実際に上演するときに、どういった方法やアイディアが、ある意味ではテキストと断絶した部分でどれだけあるのかって言うのが両方あって、その両方が地点の場合豊かだと思うんですよね。それが最終的な舞台では全部はまっているように見えると。一本の舞台を作りあげていく過程というのは、本当に試行錯誤の連続というか、稽古とかどういう風になさっているのかと思うんですよね。
三浦:それは辛いよ。新作の稽古は。
佐々木:だってほとんど何もないような状態でやるしかないですよね、これはもう。
三浦:うん、どうやってやっているってもう……お見せできないですよ。停滞していますよ、本当に。今回プロセかー……とか。策がないと聞こえないよとか。それはもう何に限らず新作を作るときっていうのは大変な思いをするわけで。何でかっていうと、スポーツに例えるのはあまりよくないんですけど、新しいルールを作らないと先にいけないんで、その方程式を作らなければならないんです。だからすごく難しいし……。『光のない。』に特化していうと、原作を読んでいただくとわかるんだけど、とにかく「わたしたち」って言いすぎなんですよ。
佐々木:印象的なのは、「わたしたち」と「あなたたち」ですよね。

三浦:それにまずひっかかるわけです。読者として。「わたしたち」ってどういうつもりかと。で、ひっかかったんで、とりあえずそこを明確にしようと。一度原作を離れて、「わたし」、「あなた」、「わたしたち」、「あなたたち」、僕らは「わたしたちゲーム」と呼んでいるんだけど、「わたしたちゲーム」をとにかく徹底的に作ってみようと。主体がどのように移ろいでいくのか。実際には本当に苦しかった。1ヶ月以上「わたしたちゲーム」。ほんの7分間のシーンですよ。「わたしたちゲーム」だけを1ヶ月本当にやりました。1ヶ月目に僕は、やっぱり幼稚だったからやめる?って。でももう立ち戻れないんですね。で、2クール目に人物を差し替えたらどうなるだろうかと粘る。「わたしたちゲーム」が通奏低音としてあれば、ポエティックなシーンに「わたし」、「あなた」と、どんどん割り込むことができる。で、やっぱりねと。こうすると意味がわかる気がする、ああ、そういうことだったのかと。勝手なる満足感とともに、コンテクスト、文脈、台詞をどういう感情でいうのか、どういう意味なのか、どういう設定なのかということをそれぞれの俳優が持ち始める。そこの作品を立ち上げるための前提はなんだったんだっけ、プロセでやるっていうのはどういうことだったっけ、ヨーロッパの最前衛のテキストをやるってことはどうだったっけということを逃げないでやると、大変ですね。何時間、何十日、ヘタすると1ヶ月。この作品は本当に1ヶ月間苦痛の連続でした。
佐々木:そこから見つけ出していくということなんですね。
三浦:そうですね。分かりやすくいうとみんなでどうやって解釈するのかということ。でも解釈したところで、芝居というのは面白くなるわけではないので、そことの葛藤もありますが。
佐々木:何度も何度も繰り返しながら、言い方を見つけていくということですかね。
三浦:まあ、集団創作と言ってしまえばそれまでですが、そのために時間を割きますし、そのために劇団の運動を止めないようにする。ある作品で培ったことは、次の作品ではあっという間に消化できますし、例えば『ファッツァー』の成功によって、再演の稽古では、『ファッツァー』のあれでやったほうがおもしろいんじゃないということも出てくる。
佐々木:そういう意味では、『光のない。』の2年ぶりの再演ということは、2年前とはいろんなことが違ってきますよね?
劇場から歩いて帰る、かけがえのない〈リアル〉
三浦:それは違いますね。当時の興奮と、いま冷静に見つめられることは全然響きも違うし、観客も違うし、それはむしろ楽しみです。こういう状況になっていて、こういったアクチュアルな作品が、アクチュアルでないとか、見ものですね。すごく楽しみにしています。余談ですが、僕は震災の時にはちょうど横浜で稽古をしていて、そのときに揺れたんですね。
佐々木:僕がトークに呼ばれていたけど行けなかったときですね。
三浦:そうですね。いろいろあって、京都に帰ったんですね。新幹線でホームにおりた瞬間にどすんって感じだったんです。平和……、あ、やばい、関西って揺れてないんだ、と思って。この違いって……と思ったことはすごく覚えています。
今回、横浜のあと、京都公演もするんですけど、京都の観客は体感的に分からない部分もあるかもしれない。横浜で初演から2年経ってやりますけど、震災からはもっと経ってますね。まあ、全然違う受け止め方になるのではないかと。
佐々木:変わっていくかというか、どう判断するかという問題なんでしょうか。
三浦:そうですね。僕らにとっては相変わらずリアリティはあるわけですよ。声届くか、とか、プロセの条件は全くかわってない。それは僕にとってはリアリティなんです。そして大問題なわけですよ、僕にとっては。演劇が全く市民権を得ていない。普通に困ってしまう。
佐々木:常に直面している問題であるということですね。
三浦:みなさんはあまり演劇とか見ないかもしれないですし、よく劇場に通う人たちばかりがここに来ているわけではないと思いますが。しかしそれもまた問題なんです。大問題というか。僕がロシアで作品を上演すると、ロンドンのグローブ座で上演すると、この前提が全く違うわけです。前提というか、観客が全く違うわけです。例えば、ロシアでチェーホフを上演するというのは、どんな風に料理しているの、と、すごく斜め目線だったり、いろいろなことに耐えなくてはならないんですが、日本にいるとそれがない。基本的に演劇が市民権を得ていないから、つまり、劇場文化というものがないから。もっと端的にいうと、こういったプロセの劇場でもどこでも、普通ヨーロッパだと、あるいはロシアだと、地図の真ん中にあるわけです。真ん中にあって、その前に広場があるわけです。で、劇を見ようが見まいがその広場で待ち合わせするんです。オデオン駅で待ち合わせっていったら、パリのオデオン座で待ち合わせってことなんです。パリ市立劇場のまえで待ち合わせとかも普通なわけです。その人たちは劇場に行かないんです。
佐々木:劇場自体がもうランドマークとして意味を持っているということですね。
三浦:そう。いざとなったらその広場を占拠してデモをするわけです。この国にはそういうことはない。第二次世界大戦以降、そういった歴史を歩めなかった、歩まなかったと言いましょうか。だから演劇がアクチュアルなわけがないです。演劇が危険なものであるという感覚が日本にはないのだから。ただし、そこの部分でどうやって演劇がリアリティを持てるのかってことは、演劇人の問題の部分もあるし、個々の観客の問題でもあるんです。『光のない。』は、その部分が深く問われている内容だとは思います。そういったところを2年ぶりに感じたいなと思っています。
佐々木:今日の講演会の題名が「演劇のアクチュアリティとリアリティ」という二つのキーワードをめぐるタイトルになっていて、いまそのお話にかかってきたと思うんですけれど。実際この『光のない。』という作品は、もともとの成り立ち自体が非常に特殊な意味でアクチュアルな作品だと思うんです。最初に作品の解説でありましたように、エルフリーデ・イェリネクという人は、ウィーンの高齢の女性の作家であるわけですけれど、彼女が日本の東日本大震災と、津波、原発事故というものを知って、それにあるインパクトといいますか、突き動かされて書いたテキストであるわけですよね。彼女は別に日本に来たこともないし、おそらく来ることもないだろうと。にもかかわらず彼女はテキストを書いて、それを2年前にフェスティバル/トーキョーで地点が上演した。もともと、依頼をされたときというのは、震災から8ヶ月くらいしかたっていなかったんですよね。ですので、いかに作品が難解だといっても、その前提自体がある種アクチュアリティを問わざるを得ないところがあり、それに対して、演出家というか、地点の三浦基として、何か言わなきゃならないとか、何か意思表明をしなきゃならないという雰囲気が、誰に問われるわけではないけどどこかにあったと思うんですよね。そこで当時のパンフレットに、三浦さんはそういったことに対して、かなり毅然とした言葉を書いてらっしゃって、僕はすごく感動したんです。で、それから2年たって、この作品が今まさにどのように観られるものなのか、この作品が訴えるものがどう変化していったのか、あるいはしていないのか、ということが今回また上演をアクチュアルにするんじゃないかなと思うんですよね。
三浦:単純に、感じてほしいことは、政治そのものとか、同時代性とかと言われるような堅苦しいことではなくて、もう少しダイナミズムというか、劇場でこういう作品が息を吹き返すというか、応答があるんだっていうダイナミズムを感じてもらえれば、少しよくなるのかなという感じがしていますね。そこからしか始まらないから。演劇をどうして人類が手放さなかったのかというと、集会をするということだからなんですね。つまり演劇が生(なま)だからいいというのは嘘で、人々がやはり集まらなきゃいけないわけ。生なのは観客なんです。私も経験ありますが、国内でも海外でも1年か10年に1回、必ず感動するときってあるでしょ。そのときってひとりでとぼとぼ帰るよね。あと、バスに乗り遅れたり、電車に乗らないで歩いて帰ったり。
佐々木:今日は歩いて帰りたいってやつですね。
三浦:そうそう、それは本人にとってかけがえのないリアルというか、問題なわけです。それは意地悪な言い方すると、わざわざ来ないと成立しないわけです。人といっしょにいないとだめな行為で、そこが生だということだと思うんです。そういう経験を誰も否定していないわけで、多分そこなだと思うんです。20世紀以降というのは映像とか映画とか、劇映画というか、同じく集まっているんですけども、また違う発展をしていっているのではないかと。感動の在り様が、あるいは収め様が。演劇というのはわざわざ足を運んで……大体の芝居はつまらない芝居ね。みんな後悔して帰るんですよ。みんな。でも後悔したくないから、食事をしたり、いろいろとお茶を濁すわけです。でも我慢していれば、1年に1回あればいいほうですけれど、10年に1回必ずやってくる。通っていれば。やばいよって時が、いてもたってもいられないときが。それはやはり社会参加だと思うんです。社会に参加しないと生きている意味がないというか。どうしても。どこの国でもどういう政治状況、政治体制であろうが、多分変わらないと思うんですね。ということを最近感じているので、そういうことをもっと自分も感じたい。僕は学生時代に感じることができたから、ラッキーにも実演家としてやってこれたんだけど、やはり最近気にしているのは観客の居場所というか、そういうことがこの作品ではすごい問われているし、問うた。イェリネクよりこちらが過剰に、問うた。だから、一番イェリネクに見て欲しいんです。私が作家をこんなに愛しているのは珍しい。
佐々木:彼女は国外へ殆ど出ないらしくて、飛行機も乗れないし、引きこもりのような人らしいですね。今日の最初のほうでの話で、この作品の上演の依頼があったときに、福島とか具体的な話が含まれているのか問うたという話があったと思います。つまり、反原発がテーマになっているようなものなのかと。この『光のない。』ももちろん原発賛成か反対かっていったら、もちろん反対だけれども、この作品、そして地点による『光のない。』の上演は豊かだと思います。僕は普通にいろいろな作品を見ていてややうんざりしてしまうのは、賛成か反対かということがわかりやすい、わかりやすいからがゆえにある強さを帯びているメッセージに同調させてしまっているような、同調しないといけないような空気というのがある時期からすごく広がったと思うんです。そういったことではなく、まさにそれは観客がいったい何を自分の中で考え直して、その作品と対峙したのか、考え始めるのか、ということだと思うんです。思考を促すという部分が、この『光のない。』という作品にはあって、それはただ単純に言葉のレベルだけじゃなくて、もっと感覚的な、光がやってくるとか、音の状態とかそういったところでできていて。終わったときにどういう作品だったとか、どんな内容なのと聞かれると、すごい作品としか答えられないところがあるんだけど、これはやはりお話というものではないという気がします。
〈わたし〉と〈わたしたち〉と〈他の者たち〉
佐々木:
そろそろ時間も後半になってきたのですが、もうひとつ、アクチュアリティということでうかがいたいことがあります。今日もお話にでてきた「わたしたち」ということについてなんです。観客は「わたし」として舞台を観ますよね、でもその「わたし」と「わたしたち」というのは一人の人間の中で常に両方あると思うんです。イェリネクは「わたしたち」という言葉をかなり強調していて、それを演出した三浦さんも「わたしたち」をどう発話するのか、つまり「わたし」が「わたしたち」をどうやって言うのかということをいろいろな形で問うた、問い直したのがこの上演だったと思うのですが、もう一方で「わたしたち」ということで、「わたし」がその中に紛れ込んで、「われわれは」といったとたんに、いきなり責任感が曖昧になったりとか、集団性を帯びて強くなったような気がするとか、ということが一方である。つまり「わたし」を「わたしたち」と言い換えることは、実はすごく難しく、それ自体が政治的な様相を強く帯びていると思うんですね。その中でどのように、観客である「わたし」と「わたしたち」に対してアプローチをしていくことがあり得るのかなと思うのですが。

三浦:それはとても大きなテーマだと思います。かつて太田省吾という演出家・劇作家が、「〈われ〉と〈われわれ〉」という演出論を書いていて、とても興味深いのですが、観客というのはどうしてひとりだと馬鹿なのに、客席に座って観客になると賢くなるんだろうと。これはある「わたし」が「わたしたち」になる瞬間なんです。群れを成すわけです。そのときに「わたし」の個的な問題というよりも、全体の雰囲気になってしまう。そういうことを常に演劇というのは突きつけられる、という意味だったと思うのです。イェリネクはその問い方をもう一枚剥いだ気がするんです。上手く説明できるか分からないんですが、「他の者たち」と彼女は言う。「他の者たち」がやってくるという、イメージで言うと自然災害だったり、津波については「海を送りつけた」とか「そこまでしなくてよかった」とか、意外と人情じゃんとか思うんですけど。「やがて他の者たちが」と言うわけです。そして最後に彼女が導き出した論法は、「放射線」とか「光」というものが「わたし」であるということ。「わたし」が「放射線」を持っている、「わたし」がその「放射能」を発してしまうというわけです。これは説得力があるわけです。つまり、東電の人であろうと、ほうれん草を買えない主婦であろうと、誰であろうと「わたしたち」が人類の先端に生かされていて、たまたまだけどこういった事故があったときに、「わたし」が「光」を発しているんじゃないだろうか、「わたし」が判断をしてきたんじゃないか。そして最後に彼女が突きつけてきたものは、政治性そのもので、観る前から言っちゃうけど、「あなた」あるいは「あなたたち」の「判決」をくれというわけです。ここに、ダイナミズムというか、いろいろ問うんだけど、おまえたち、黙ってないで判決をしてくれよ、判断しろというわけです。これはアジテーション演劇だし、演劇の本来もっていたオリジナルなものだと思うんです。飛躍しますが、2000年前のギリシアだとして、みなさんがそこにいるとして、私が演者だとして舞台上で何をするかっていうと、自分の子どもを殺す芝居をするわけですよね。タブーを見せつけるわけです。で、観客は、ああ、こういうことやったらまずい、と思うわけです。事件を目の当たりにする。イェリネクが言っているのはそういった歴史性、そこの部分にかならず立ち返る勇気を持っているし、彼女にとっては、誤解を恐れずに言うと東日本大震災も原発もひとつのモチーフです。ひとつのモチーフでしかない。もっともっと長大な辿らなきゃいけないもの、その氷山の一角であるということなんです。
佐々木:巨大で遠大なものを扱っているということですね。
三浦:『光のない。』という作品を原発賛成か反対かという二元論に陥らせると危ないと感じるのは、原作のそういう部分を感じ取ったからだと思います。「他の者たち」の力、それはもしからした科学かもしれないし……音波とか音とかも大きなテーマとしてあるんですよね。今回再演していて思うのは、第一バイオリンと第二バイオリンの関係性ですね。
佐々木:第一バイオリンと第二バイオリンというのがAとBの、まあ役名としてというと変ですがあるんですね。
三浦:まあ、オーケストラという社会があるとすると、その中での第一バイオリンと第二バイオリンとの関係性。つまりヒエラルキーがあるわけですね、クラシックの楽団の中に。そういったものもまたモチーフにされているし、世界の構造を紐解いてみせるようなかたち、その中で責任の所在が一番分かりにくくなった問題が、放射能の問題でしたし、原発の問題でしたね、ということのような気がします。「わたし」が「わたしたち」になる瞬間というのは実は個々人が沢山経験しているわけです。テレビの前でも新聞を読んでも経験している、つまりメディアを目の前にしたときに、人はそれしか経験していない。そういうことのもうひとつ外側から「他の者たち」という言い方をしちゃったというのはなかなか面白いし、今回の演出でもそこには多分十分に応えられていないと思う。台詞は滑っていると思う。チェックしてほしいんですけど、多分適当にごまかして言ってると思う。分からないんですよね「他の者たち」って。ロボットじゃだめだな、宇宙人レベルじゃないと、鹿とかが出て来て日本語しゃべってくれないと。
佐々木:他の者と言うなら、本当に他の者じゃないといけないと言うことですよね。
三浦:そうそう。だからそこは僕もわからないし、イェリネクもわからない中の手探りで書いているんだろうなと思うんだけど、ちゃんとは答えられない、大きいテーマだったと思います。
質疑応答(1)ドラマトゥルクを愛せ
〜コラージュ演劇のつくり方
佐々木:せっかくこれだけ沢山の人が集まってきてくれたんで、質問を受けようと思うんですけれども。意見でもいいいんですが。
観客1:作品の作り方についてもう少しお伺いしたいです。今回の『光のない。』に関しては、どのようにしたらその言葉を発していけるのか、ということを試行錯誤していく、とお話されていましたが、他のチェーホフですとか、太田省吾、アルトーなどのコラージュ作品の場合は、どうしたら言えるのかということはまた別の問題として立ち上がってくると思うんですけれども、そういう作品については作り方みたいなところから違うものなんでしょうか。
三浦:チェーホフの場合は四大戯曲全て演出しているんですが、装置というか舞台美術から考えます。たとえば『ワーニャ伯父さん』だったらピアノから降りないとか、「環境」と呼んでいるんだけど、舞台美術と呼ぶより舞台装置と言う方が好きなんですが、俳優がどういう風にその装置の中で機能していけるのか、そうしたことを気にするんです。例えば、テーブルにのっかったまま、この人は妄想してしゃべり続けるとか、そういう設定。そうすると、モノローグがドンとしてくる。ダイアローグよりも、かいつまんで固めてモノローグにしちゃう、というような感じですね。チェーホフをライフワークにして長いので、最近変ってきたりもしていますが、基本的には妄想のありかをどういう風につくるかということから、語りということを意識してつくりました。
アルトーや太田省吾の作品のように、評論などのコラージュの場合は、あまり上手くいかないです。難しい。頭で考えてしまうんです。台詞があって、このワンシーンやって、ここで本人が書いた批評的な文章かぶせよう……みたいなことは、構成を責任をもってやってくれる人がいると上手くいくと思います。でも自分たちだけで集団創作していると、どうしてもそこの偏差値が低くなっちゃう。俯瞰できないからかな、それは上手くいかないんで、方法とかはないんです。
ただ、ひとつ、『CHITENの近現代語』という、隠れた名作と呼んでいるんですが、大日本帝国憲法とか、玉音放送とか、朝吹真理子さんの短編からの引用とか、ものすごい細かい単位で構成してるものがあって、これはすごくいい。桜井圭介さんがアドバイスしてくれたんです。ドラマトゥルクとして、初期の初期の段階で、こんな感じというのを言ってくれて、最初はほんとに?と思いながら言われた通りにやっていったんですが、そういった限定、ひとりの人の頭で考えた、物語ではないんですが、囲み方があると、演出や俳優の作業というのは、彼の嘘かもしれないけど、その思いをなんとかつなげてあげようという感じで、上手くいきますね。
コラージュ演劇をやりたい場合は、かならずドラマトゥルクをつけたほうがいいです。その人が頭が悪くてすごいロマンティストだったとして、その人を愛せばいいだけです。それが現場の仕事。とにかく、そいつが、どれだけ病んでてどれだけロマンチストかということを、なんとかみんなで愛したらうまくいく。
佐々木:作者じゃなくて、コラージュする人を愛せってことなんですね。
三浦:そう。で、作家は死んでいるほうがいい、理想は。著作権がないほうがいい、とにかく。これは本当です。これは本当のアドバイス。刺激的な作品を作ってやろうというときは、とにかく著作が切れているもの、作家が死んでいるもの。絶対文句言われないから。

佐々木:だれもがイェリネクみたいな人とは限らないですからね。
質疑応答(2)群舞とマスゲーム
〜死の表象と演劇
観客2:三浦さんが書かれていることや、最近の作品をみて、土方巽さんの論考について考えまして、「群舞は可能か」ということについてなんですが。三浦さんはそれを演劇で実践しているのかなと思って見させていただいているんですけれども、演劇は基本的に群舞であると思うのですが、それを三浦さんがどう問われて、そして達成していると評価しているのか、お聞きしたいです。
三浦:今彼が言っていることなんですが、土方巽という舞踏家がいて、もちろん伝説の舞踏家ですね。ソロはみなさん映像で見たことあるかもしれませんが、「突ったったまま死んでる」というような、もう、泣くよ。ビデオで観ても、ああ、すげえというか、ああ、と思いますよ。で、その後カンパニーを組むわけですよね。そうすると、見るに耐えないんです。これアウトだよねと。かたや、パリ・オペラ座でローラン・プティなんかの振付を見てご覧なさいよ、素晴らしいですよ、群舞も。やはり西洋の上へ向うバレエと、下へ向う舞踏というのは違うなと。それはシステムの作り方の問題なんですよね。バレエは譜面化されているし規則化されていて、土方は舞踏譜というかたちでやろうとしたんだけど、一般的じゃないわけですよ。そうすると徒党を組もうというときに考えないダンサーが集まると、それはやはり無理があるんですよ。指導する側もいらつくから、だからそこにはある程度の完成度しか求めなかったんだなと、もう少し頑張ってほしかったなというのが、僕の土方の見方です。
いま彼が指摘したのは、群舞に準ずるような形、今日の話に引きつけていうと、「コロス」ですね。合唱とか、同時に人は同じ事ができるのかとか。例えば北朝鮮のパレード、誤解を恐れずにいうと素晴らしいわけですよ。あの膝の上がり方。いわゆるマスゲームですね。舞台というのはそういう歴史がある。固有名詞がついてないものが圧倒的な力を示す、それで高揚するということはあるんですね。パリ・オペラ座では、ダンサーが3歳から踊り始めて、しかも難関をくぐってきているわけだから、当然技術的に鍛えられて、一生同じことをやっているわけですから、何でもできるわけです。そしてそこに感動してしまう自分もいる。だから群舞とか合唱とか、集団の動きみたいなものの完成度はどこまでいってらっしゃいますか、という鋭い質問なんですね。それはあまりうまく行ってないからPiriPiriの力を借りるわけです。そのほうが素直だろうなということで。今までわだかまっていたものが、ざまあみろというか。ぶんぶん腕が動いてもたかが知れているわけですけど、そこに袖をちょっと直すようなナチュラリズムを入れてみるんです、そこにビン!ときたらお客さん騙されるかなとか、もうちょっと手を高くあげろ、とか。多分群舞とか、マスゲームとかいうものは、人を人として見ていなくて、死んだものの塊として見ているわけですよね。死の表象されたものだと思うんですね。それが外圧によってそういうことができるって事が、棚ぼただけど上手く行ったと思います。
あとは、いまの質問に答えると、合唱隊をぜひご覧ください。12名なんですけど、この人たちは「蛇居拳算」と呼ばれている三輪さんが作ったアルゴリズムのシステムを使って歌っていて、非常にファジーに出来上がっているんですけど、なんだか群れというか群舞感を出しているので、それはひとつの回答なんだと思うんですよね。現代作曲家が「コロス」というものをどのように支配するか。そこには偶発性が伴っていて、最初に三浦さん見てくださいといって数字の表を見せられたわけです。ここから始めると、必ず何十回目には初期値に戻りますと、嬉しそうに言われるんですけど、これ劇で使うのは一部分ですよねという話をしたわけです。だけど、そういった観念があるわけです。土方の失敗は踏めないと。踏まない。難しい問題だと思うね。
佐々木:三輪眞弘さんは本当に現代音楽と呼ばれる分野で、間違いなく最も先鋭的な活動をしている作曲家だと思います。その彼と地点とのタッグというのもぜひ注目していただきたいと思います。
質疑応答(3)演劇の社会的地位を上げるためにはどうしたらよいか
観客3:日本国内における演劇の社会的地位を上げるためにはどのようなことをすればよいと思いますか。
三浦:誰が?俺が?みんなが?
観客3:みんながです。
三浦:これは大きいね。みんな観に来てよ。まずはそれだよ。それはまあ、砂漠に水を撒くようなものだけれども、やはりこれだけの人が集まってくれて、これだけ熱心に聞いてくれて、芝居観に行きませんでしたというのはなしにしようよ。
佐々木:まあ、みなさん絶対に観にいきたくなったと思いますけども。
三浦:まず、気持ちはよく分かります。まあでもね、そんなに良くならないから、基本的には。状況はね。ただそこで、悲観しないことだと思うよ。別にいい芝居を観にいきたいんだったらベルリンに行けばいいじゃん、パリにいけばいいじゃん。そういう人はいっぱいいる。僕もパリで2年間で、多分600本以上見ているけど、2本か3本だよおもしろかったの。
佐々木:まあでも3本観れたからよかったと思うわけですよね。
三浦:別にそんなもんだと思いますよ。そこはさ、日本を飛び越えよう。いい芝居を観るために、いい舞台を観るために。それでいいと思う。でもそれだと状況はよくならないんじゃないか。先鋭的な研究か、下手すると一ファンで終わるよね。で、その人の私生活の中で、結婚したり、状況変わったり、東京から離れたり、子どもできたり、演劇からどんどん離れていって、若い頃はああいうの見たなとなる。それはよくないと思う。よくないと思うけど、どうしようかね。僕がどうするかだったらいえます。僕だったら、例えば、国立劇場の芸術監督になります。そうすればあなたの不安を解消できるようなプログラムを用意します。もちろん。劇場で俳優を雇用します。とか、いくらでもアイディアはあります。でも残念ながら、誘ってくれる役人もプロデューサーもいません。だから今僕にできることは、ロシアにちやほやされているから、ロシアのどっかの芸術監督になるんじゃないですか。そうしたら日本の人は目を向けてくれるかもしれない。出た、逆輸入パターン。それは屈辱的でそうなりたくない。そういった努力は本にも書くから、応援してっていう感じです。でもでかいことは言えないな。まずは芝居を観ることだな。
佐々木:実際そういうことですよね。まず劇場に足をはこぶ、『光のない。』を観にいくかどうか、というのが第一に今日の話につながるのではないでしょうか。
90分、非常に濃密な話で、床に座ってらっしゃる方もいるくらいの状況で、沢山のみなさんに聞いていただいてありがとうございました。三浦さんもお忙しい中ありがとうございました。10月11~13日の3日間でKAAT神奈川芸術劇場で『光のない。』上演されるということで、僕も拝見しに馳せ参じようと思っている次第です。
本当に今日はどうもありがとうございました。
三浦:ありがとうございました。

